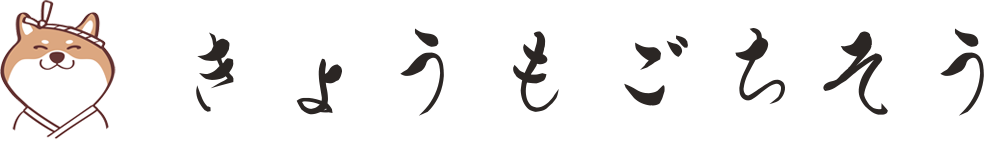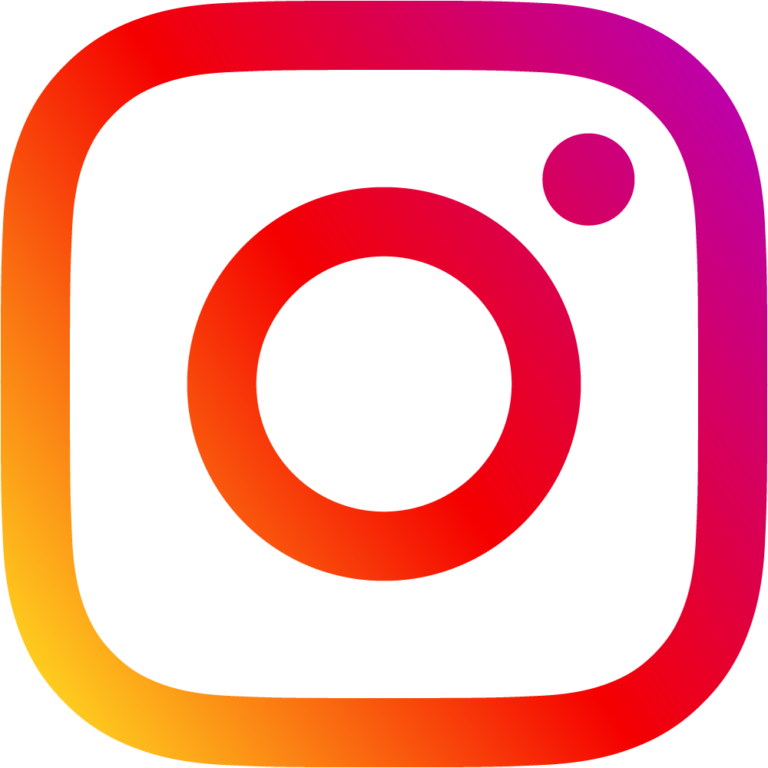残暑バテに要注意!愛犬の体調管理とおすすめの食材
※本記事はペット栄養管理士の資格を有する執筆者が監修しています。

夏が過ぎたと思っても、残暑は続きます。人間にとっても疲れが出やすいこの時期、実は犬にとっても体に大きな負担がかかっているのをご存じでしょうか?
この記事では、残暑バテが犬に与える影響や見逃しやすいサイン、そして食事や生活習慣でできるケア方法をご紹介します。
1. 残暑は意外とキケン?犬の体に起こる変化とは
残暑とは、暦の上では秋に入っているのに夏の暑さが残る時期を指します。日中の気温が高いままで朝晩との寒暖差も激しくなり、自律神経に負担がかかりやすくなります。
犬は人間よりも体温調節が苦手な動物。とくに体の小さい犬や高齢犬、短頭種(パグやフレンチブルなど)は、暑さの影響を受けやすいため注意が必要です。
2. 残暑バテの主なサインとは?
次のような様子が見られたら、残暑バテの可能性があります。
- ☑︎なんとなく元気がない・寝てばかりいる
- ☑︎食欲が落ちてきた・おやつしか食べない
- ☑︎便がゆるくなる、または回数が増える
- ☑︎体が熱っぽい・呼吸が荒い
- ☑︎散歩に行きたがらない・途中で止まる
3. 原因は?体温調節・自律神経・食欲の変化
残暑バテの原因は多岐にわたりますが、主に以下の3点が挙げられます。
- ☑︎体温調節の負担:朝晩の寒暖差が大きくなり、体がうまく適応できない
- ☑︎自律神経の乱れ:日中の暑さが継続し、交感神経が優位になりやすい
- ☑︎胃腸機能の低下:夏の疲れが残り、食欲が不安定になりやすい
こうした影響が重なることで、食欲不振・便の不調・元気消失などの体調変化が表れます。
4. 残暑バテを防ぐ体調管理のポイント
残暑バテを防ぐには、以下のような基本的なケアがとても効果的です。

- ☑︎エアコンや扇風機を活用し、室温を25〜27度前後にキープ
- ☑︎冷たい床で寝かせず、クッションやマットで保温・保湿を
- ☑︎お水は複数箇所に置き、飲みやすくする
- ☑︎散歩の時間帯は早朝または夕方以降に限定
- ☑︎夜の気温が下がる日は、服や腹巻きで保温を
「夏より少し過ごしやすいから大丈夫」と油断せず、引き続き熱中症や脱水症状への注意が必要です。
5. 体を整えるおすすめの食材&トッピング
食事からのケアも大切なアプローチ。残暑バテを防ぐためのおすすめ食材を紹介します。

- ☑︎鶏むね肉・鹿肉:高タンパク低脂質で、消化にもやさしい
- ☑︎サツマイモ:エネルギー源+腸内環境サポートにも
- ☑︎かぼちゃ:βカロテンや食物繊維が豊富
- ☑︎甘酒(犬用):ブドウ糖やアミノ酸、ビタミンで疲労回復にも◎
- ☑︎青汁パウダー(犬用):抗酸化ケアや腸活に最適
あくまで主食に対する「トッピング」として使い、与えすぎには注意しましょう。
6. 食事でできる予防と回復ケア
愛犬の便がゆるくなった、あるいは元気がないときは、以下のような工夫も有効です。
- ☑︎お湯でふやかしたフードを使って胃腸の負担を軽減
- ☑︎トッピングには消化に良い温野菜を
- ☑︎便が緩ければ乳酸菌・オリゴ糖などの腸活素材を追加
- ☑︎水分量の多いフードで脱水防止
7. 残暑の脱水と水分不足に注意
暑さのピークは過ぎても、残暑が続く時期は思いのほか汗をかきやすく、犬も体内の水分が失われやすい状態になります。特に散歩中や室内が蒸し暑い環境では、知らず知らずのうちに軽い脱水を起こしていることも。
水分が不足すると、以下のような不調につながります:
- ☑︎便が硬くなりやすく、排便トラブルに
- ☑︎腎臓への負担増
- ☑︎食欲低下やぐったり感
対策としては、以下のような工夫がおすすめです:
- ☑︎水飲み場を複数設置し、いつでも飲めるようにする
- ☑︎水分の多い食材(ゆで野菜・ウェットフードなど)を活用
- ☑︎甘酒やスープなどをトッピングして水分補給を促す
シニア犬や腎臓に不安のある子は、特に水分摂取を意識的にサポートしてあげましょう。

犬用青汁(国産・無添加パウダー)
野菜の女王とも呼ばれるほど栄養豊富でバランスがいいプチヴェールを使用。プチヴェール100%でできた青汁パウダーは、残暑バテによる腸の不調や食欲の乱れにアプローチ。免疫ケアにもおすすめのトッピング素材です。
▶ 商品を見る7. まとめ|「夏の終わりこそ油断せず」が健康の秘訣
残暑は短いようで、犬の体にとっては意外とストレスの多い季節です。夏の疲れをしっかり癒し、食事と生活環境を整えて、秋の健康をスムーズに迎えましょう。
いつものごはんにほんの少し手を加えるだけでも、体はグッと楽になります。季節の変わり目にこそ、丁寧なケアを。